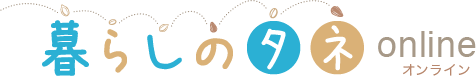命を守るためのアクション
災害時のAtoZ

近年、地震をはじめとする自然災害にいつ遭遇しても不思議ではありません。また、暮らしの中でもちょっとした不注意で火災になることもあります。不慮の災害への備えや、命を守る行動のAtoZを学び、今すぐ対策することをお勧めします。
災害への備えや発災時の適切な
行動はマナーです
今、大地震が起きて、震度6強の揺れに襲われたら、あなたはどうします?そして火災やガス漏れ、長期の断水、停電、ガス停止、更に通信、物流の混乱も想定されます。備えるということは、結果事象にも備えることです。では、何をどう備えれば? まずは「安全な場所に住む(する)ための防災」の実践です。「安全な場所に住む(する)ための防災」には、家の耐震化、家具の転倒落下防止対策、ガラス飛散防止対策などはもちろん、ライフラインが止まっても家族が生活できるための準備が大切です。大規模災害に備えるには、少なくとも1週間分の備蓄が必要。下 A の「備蓄品」を参考に、高齢者や乳幼児向けに追加して用意すべきものなどを家族で話し合ってみてください。

備えあれば憂いなし!
自宅と車に用意しておくべき備蓄品


東日本大震災発生時、東京でも食料や生活用品が店頭から消えたことを覚えているかと思います。災害時に本当に物を必要としている被災地への供給を妨げないためにも、普段から一定の備蓄をしておくことは、災害の多い日本に住む者のマナーだといえます。
また、災害時の行動について事前に家族と話し合うことも重要です。年に1、2回の頻度で、緊急連絡先や避難方法などを話し合いましょう。その際、3つのポイントを念頭において話し合うことを心がけてください。
災害時の行動①連絡方法
離れた親戚や友人の家に、家族一人ひとりが安否確認の連絡を行う「三角連絡法」を実践しましょう。
災害時の行動②集合場所
広場や学校など、家族が落ち合う場所を決めておきましょう。
災害時の行動③在宅避難と分散避難
大雨・土砂災害等による警戒レベル4「危険な場所から全員避難」というのは、危険区域で災害懸念のある人が対象です。自宅の安全が確認できた人は、自宅で暮らす「在宅避難」が原則です。電気、水道が止まっていても感染症の心配もなく、よく眠れます。避難する場合も、避難所だけでなく、2階への垂直避難、自治会館、親戚・知人宅、車中避難などの「分散避難」を検討します。
また、地震や火災が起きた場合でも、迅速に行動できるようにしておきます。まずは、下 B の手順を頭に入れておいてください。

出火時等の対処法4つの手順
 1 知らせる
1 知らせる
火災が発生したら、「火事だ!」と声をあげたり、笛を吹いたりして近くの人に知らせます。そして、119番通報します。自分だけでなんとかしようとすると煙や炎が広がり、逃げ遅れる危険性があります。
 2 消す
2 消す
火災が発生したら、すばやく消しましょう。出火から3分以内なら、消火器や水を使って消せる場合があります。ただし、天井に燃え移ると、一度に火が広がるフラッシュオーバーの危険があるのですぐに避難します。
 3 助ける
3 助ける
自分の安全を確保しつつ余裕があれば、逃げ遅れた人がいないか呼びかけ確認しましょう。もし助けが必要な人がいたら、周囲に応援を求め協力して姿勢を低くして安全な場所まで誘導します。
 4 逃げる
4 逃げる
天井に火が付いたり、煙が充満してきたら、直ちに姿勢を低くして安全な場所に避難しましょう。全員避難を確認した上で、他への延焼・拡大防止のため、部屋や玄関ドアを閉めて空気を遮断します。
次に、シチュエーション別の命を守る行動です。緊急地震速報や地震の揺れを感じたら、閉じ込められないように、まず避難経路の確保が大切です。
シチュエーション①自宅
すぐに玄関のドアを開けましょう。比較的狭く柱の数が多い玄関は安全ゾーンと見なされ、避難に適しています。実際、被災地で倒壊した家を数多く見ましたが、玄関だけがそのまま残っている家が多くありました。手を放しても閉まらないようにドアストッパーをかけ、倒壊の危険があれば外部に脱出します。
シチュエーション②オフィス
ドア付近にいる人はドアを開け、安全ゾーンに移動、間に合わなければ机の下などに潜ってください。
シチュエーション③地下鉄
車内に煙が充満したり浸水してきたら、係員の指示がなくても非常用コックを開き、安全確認後避難しましょう。係員の指示を待つのが原則ですが、常にその指示が正しいとは限りません。
シチュエーション④屋外
ガラスや看板が落ちてくる危険がありますので、まず建物から離れましょう。車を運転していたら、ハザードをつけて徐行、左側に寄せて停車します。
いずれの場合も、その場の安全ゾーンを確認し、自ら避難して命を守る必要があります。火元やガス栓の確認は揺れが収まってからで構いません。
津波の危険がある場合、警報の有無にかかわらず避難し、最悪を想定して遠くより高所に逃げ、避難した後は警報解除まで、元の場所に戻らないようにしましょう。たとえ1人でも避難するよう心がけてください。
また、インターネットやスマートフォンでの情報収集も有効。事前に公的機関の防災メールや防災アプリを入れておくと安心です(下 C 参考)。ただし、SNSはデマが流れることもあるので、複数媒体での確認が大切です。

安否確認や情報取得に活用したい
インターネット&アプリ


※この記事内容は、執筆時点2025年8月1日のものです。
 山村 武彦(やまむら たけひこ)
山村 武彦(やまむら たけひこ)
防災システム研究所所長。50年以上にわたり、国内外で発生する災害の現地調査を行なっている。企業や自治体の社外顧問やアドバイザーを歴任する。連載や著書多数。