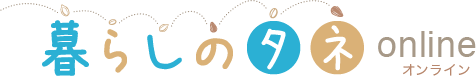大掃除いらずで新年を迎える!
「分割掃除」術のススメ

大掃除というと年末に一気にやるイメージですが、忙しい現代の暮らしにはなかなか難しいもの。だからこそ秋から始める“分割掃除”で無理なく行うのがおすすめです!「計画・下準備」、「キッチン・ダイニング」、「リビング」、「水回り・玄関」の全4回に分けてポイントをお伝えします。下準備が整ったら、まずは大物の「キッチン・ダイニング」からスタートしましょう。手間がかかるイメージですが、手順を押さえれば効率的にピカピカにすることができます。
1.分割掃除は、最も汚れが
溜まりやすいところから
家族が毎日食事をするキッチン・ダイニングは、家の中でもとくに汚れが溜まりやすく、掃除の手間もかかる場所です。そのため、分割掃除では最初に取り掛かるのが効率的。余裕のある時期に済ませておくことで、年末の負担がぐっと軽くなります。また食欲の秋にキッチン・ダイニングをキレイにしておくことで、より一層食を楽しめます。
前回記事の「計画・下準備編」を参考に、掃除の下準備を整えたら、キッチン・ダイニング全体の埃取りから始めていきましょう。
2.“上から下へ”がコツ!
まずは埃取りから始めよう
埃取りの基本は「上から下へ」。天井→壁面→背の高い家具→背の低い家具の順番にはたきなどで軽く撫でるように埃を取っていきます。上から下に取ることで、落ちた埃をまとめて処理できるので、掃除がスムーズに運びます。

<用意するもの>
・はたき
・孫の手ハンガー
手の届きにくい場所には「孫の手ハンガー」
照明器具、エアコン周り、カーテンレールの上、家具の上など、手が届きにくい場所は「孫の手ハンガー」を使うと、幅や角度を調節しながら埃が取れるのでおすすめです。
お家にあるもので簡単にできる!
掃除グッズ「孫の手ハンガー」
<用意するもの>
・針金ハンガー
・タオル
・ストッキング
※いずれも使い古しのものでOK

<作り方>
1.ストッキングを片足ずつにカットします。
2.針金ハンガーを縦に伸ばし、2つ折りにしたタオルをハンガーの間に巻き付けます。
3.ストッキングの片足部分を被せて結びます。
針金を好きな場所で曲げて、形を自由に変えられるのがポイント。壁の隙間や棚の上など、手の届きにくい場所のホコリも楽に掃除できる、まさに“孫の手”のようなアイテムです。ストッキングの柔らかく細かな繊維が汚れをしっかりキャッチしてくれるので、家具や壁を傷つけにくいのも安心です。
近藤先生からの
ワンポイントレッスン

「埃を取ってから掃除をする」ことの重要性
家具の上や照明器具にたまった埃を取らずにいきなり掃除機や拭き掃除をすると、後から埃が舞い落ちて二度手間になります。最初に埃を落とすことで、掃除機や拭き掃除の仕上がりが格段にアップします。天井、壁、照明器具がきれいになると、部屋の明るさがぐんとアップしますよ。
また、冷蔵庫の上は、埃や油汚れがたまりやすい場所。掃除をした後にラップを敷いておけば、次はそのラップをはがすだけでお手入れ完了!ラクにキレイをキープできます。
3.効率よくキレイにするには“手順”が鍵!キッチン掃除のコツ
キッチンは、家の中でもとくに汚れが溜まりやすい場所。油汚れや焦げ付き、食品カスなど、放置すると落としにくい頑固汚れに変化します。だからこそ、掃除の順番を意識するのがコツ。無駄なく効率的に進めるための手順を紹介します。

<用意するもの>
・ゴミ袋(70L程度)
・つけおき用洗剤
・油汚れ用洗剤
・クリームクレンザー
・スポンジ
・スチールウールたわし
・キッチンペーパー
・ラップ
・新聞紙
・ヘラ(使わなくなった樹脂製のカードなどでもOK)
<掃除手順>
1.部品のつけおき洗剤液を作る
シンクの内側に大きめのゴミ袋(70L程度)を敷き、ガムテープでずれないように固定します。その中につけおき洗剤を入れ、お湯(40〜50℃)を足して、洗剤液を作ります。ゴミ袋を敷くことにより、浮き上がった汚れでシンクを汚さずに済みます。
2.部品を解体し、つけおきする
換気扇のフィルターやファン、コンロの五徳など、外せる部品を順に取り外します。1で作った洗剤液の中に入れ、しばらくつけおきして汚れを浮かせましょう。ネジや小さな部品はなくしやすいので、コップなどに洗剤液を少量とり、別でつけおきすると安心です。
3.目立つ油汚れを取る
レンジフード内やコンロの目立つ油汚れは、あらかじめヘラでこそげ取りましょう。
4.全体に洗剤をスプレーし、「湿布」する
油汚れ用洗剤の働きをより効果的にするために、前もって換気扇からガス台まで、全体的に水を含ませたスポンジで表面をなでるように湿らせていきます。あらかじめ湿らせておくことで、キッチンペーパーがぴったり貼り付きやすくなります。その上からキッチンペーパーを貼り、油汚れ用洗剤をまんべんなくスプレーして「湿布」します。換気扇の外側や壁面などは乾燥しやすいので、キッチンペーパーの代わりにラップを使うと効果的です。10分以上そのまま置いておくことで、こびりついた油汚れが浮き上がり、後の拭き取りがぐんとラクになります。
5.部品の洗剤洗い、すすぎ、乾燥
湿布している間に2.でつけ置きしていた部品を洗っていきましょう。シンク内の洗剤液とスポンジで浮き上がった汚れをこすり落とし、いったん新聞紙の上に仮置きしておきます。次に、シンク内の洗剤液を流して、空になったシンクの中で部品を水またはお湯でしっかりとすすぎます。最後に乾いたぞうきんや布で水分を拭き取り、よく乾燥させておきましょう。
6.拭き取り
3.の湿布を、汚れを取りながら外していきます。4.でスプレーしていた部分も含めて、汚れが浮き上がってきているので、スポンジたわしでこすり洗いした後、水拭き、乾拭きの順で拭き取ります。
7.頑固な汚れを落とす
コンロなどの頑固なこびりつきは、スチールウール・クリームクレンザーを使って落とします。割り箸・竹串でこそげ落とすのも手です。
8.部品の取り付け
5.で乾燥させた部品を取り付けていきます。
9.調理台・シンクの仕上げ
仕上げに調理台とシンクをクリームクレンザーで磨いて、終了です。
4.食卓空間を心地よく整える!ダイニング掃除の進め方
ダイニングは食べこぼしや油の飛び散りなど、日常の小さな汚れが積み重なりやすい場所です。頑固な汚れに注意しながら進めましょう。椅子の脚裏やテーブルの脚元など、普段見落としがちな部分も忘れずに。ここをきちんとケアすることで、ダイニング全体の清潔感がぐんと高まり、毎日の食事がさらに気持ち良く過ごせる空間になります。

<用意するもの>
・竹串
・布(使い古しのものでOK)
・掃除機
・住まい用洗剤
・ぞうきん
<掃除手順>
1.目立つ汚れを取る
固まった食べこぼしや床の溝の汚れは、竹串に布を巻き付けてかき出します。
2.掃除機がけ
目立つ汚れを取った後、掃除機がけをしていきます。椅子の脚周りやテーブル下はホコリや食べカスが溜まりやすいので、念入りに。
3.拭き掃除
水で薄めた住まい用洗剤をぞうきんに含ませ、床を拭きます。その後、水で清め拭きします。テーブルや椅子も同様に。
まとめ
キッチンとダイニングは家族が集まる場所であり、汚れやすくもあるスペース。だからこそ、年末にまとめて取りかかるよりも、秋から少しずつ進める“分割掃除”がおすすめです。最初に埃を落とし、効率良く油汚れや食べこぼしを落としていけば、無理なく清潔をキープできます。今回紹介した「孫の手ハンガー」など身近なアイテムも活用しながら、気持ち良く新年を迎える準備を進めましょう。
次回は、家族の物が集まる「リビング」をスッキリ整理していきます。
※この記事内容は、執筆時点2025年10月22日のものです。
 近藤 典子(こんどう のりこ)
近藤 典子(こんどう のりこ)
一般社団法人ホーム&ライフ協会近藤典子代表理事。住まい方アドバイザー/インテリアコーディネーターとして収納や家事動線、掃除の工夫など暮らしを快適にする提案を行っている。テレビや雑誌など多くのメディアに露出。著書は50冊近くあり、累計販売部数は400万部以上。これまでに住まいに関わり、生活の質を高める空間づくりを実践。住まいに関する知恵やノウハウを伝える活動を展開。現在、社会問題となっている空き家対策として、親の家を片付ける活動に力を注いでいる。