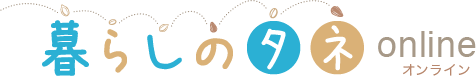突然のケガや不調にどう対処する?
「応急手当」の基本

自分や家族が突然のケガや不調に見舞われたとき、慌てずに対処できるよう応急手当の基本的な知識を持っておくことが大切です。出血ややけどなどのよくある症状の手当や、家庭に備えておきたいアイテム、救急車を呼ぶかどうか迷ったときの対処について、救急の専門家に教えていただきます。
もしものために知っておきたい応急手当の基本
日常生活の中で起こりやすい出血・切り傷、やけど、捻挫・打撲・骨折、熱中症といった症状の手当のポイントを紹介します。症状によっては医療機関による適切な処置を受ける必要がありますが、その場合でも受診までの間に悪化させないために、応急手当をぜひ知っておきましょう。
■出血・切り傷
ケガをして出血した場合は、出血している部位を圧迫して止血します。ガーゼやハンカチなどを当ててその上から圧迫すると良いでしょう。
かつては止血のために根元を縛る方法も用いられましたが、応急手当としては現在では推奨されていません。血液からの感染予防として、ビニール手袋やビニール袋の上から止血すると安心です。
軽い切り傷や擦り傷の場合は、まず水道水など清潔な水で洗い流します。しっかり洗った後は、傷口は消毒せず、ワセリンを塗ってガーゼで覆うことで、より早く、きれいに治りやすくなります。

■やけど
やけどをしたら、すぐに流水で患部を冷やします。10分以上は冷やし、熱を取り除きましょう。服の上から熱い汁物などをこぼしてしまった場合は、無理に脱がさず服の上から流水をかけて冷やします。
症状が軽い場合は、ワセリンを塗ってガーゼで患部を覆います。水膨れができている場合は破らないようにそっと冷やし、ガーゼなどで覆って保護した後、皮膚科を受診しましょう。

■捻挫・打撲・骨折
捻挫や打撲の場合は、腫れを防ぐために患部を冷やし、できるだけ動かさないようにしましょう。
患部を少し動かしただけで痛む場合は、添え木や棒で患部の前後の関節を固定します。たとえば患部が前腕ならば、手首と肘が動かないように固定しましょう。添え木は、真っ直ぐで折れないものなら何でも構いません。

■熱中症
暑い日にめまいや吐き気がある場合は、涼しい場所に移動します。衣服を緩め、首や脇の下、股の付け根など、太い血管が流れている場所に保冷剤や氷のうを当てて体を冷やしましょう。
意識があり、水を飲める状態であれば、塩分を含む飲料を補給します。吐き気があって水分補給できない場合や、意識がもうろうとしている場合は、すぐに119番に電話しましょう。

他にもある!家で起こりうる不調
誤飲・のどに詰まった場合はすぐ相談
子どもやお年寄りが洗剤や医薬品などを誤って飲んでしまった場合は、無理に吐かせず、何をどの程度飲んでしまったかを確認し、速やかに医師や救急窓口に相談します。

固形物や食べ物を詰まらせてしまい、顔色が悪い、苦しそう、息ができないといった様子が見られるときは窒息が疑われます。すぐに119番に電話しましょう。救助者はまず背中を強く叩いて異物の除去を試みます。対処方法が分からない場合は、救急隊員に指示を仰ぎましょう。
冬場はヒートショックに注意

ヒートショックは、急激な温度変化によって血圧が急上昇・急下降し、心臓や血管に負担がかかり起こります。特に冬場はお風呂に要注意。脱衣所と浴室の温度差が大きく、高齢者や持病がある人がなりやすいといわれています。意識のない人を発見した場合は、すぐに119番に電話しましょう。対策としては、入浴前に脱衣所や浴室を暖めて急激な温度変化を避けるように。また、入浴中は水分が体から失われるので、入浴前にコップ1杯程度の水を飲んでおくのがおすすめです。
備えておきたい救急アイテム
いざというときのために、家庭や外出先で役立つ救急アイテムを備えておくと安心です。

■家庭で揃えておきたいもの
・ワセリン:ケガややけどをした部位に塗って乾燥を防ぎます。
・ガーゼ:ワセリンを塗ってからガーゼで覆い保護します。
・テープ:ガーゼを固定するのに使います。
・三角巾:固定した腕を吊るすために使用します。また、細めに折りたためば包帯の代わりにもなります。
■外出時に携帯したいアイテム
・マスク:感染症の予防や、急な応急手当が必要なときに持っていると安心です。
・ビニール袋:直接血液に触れることを防げます。

迷わず119番!
救急車を呼ぶべき緊急症状
応急手当では対処しきれない場合や、命の危険があると判断した場合は、ためらわずに119番に電話しましょう。
特に以下の症状がある場合は、速やかに呼ぶ必要があります。

・胸の激しい痛みや息苦しさ:心筋梗塞
・ろれつが回らない、片側の手足が動かない:脳卒中
・蜂刺されや食後にみられた呼吸困難やじんましん:アナフィラキシー
・異物をのどに詰まらせて息ができない:窒息
・運動中に突然倒れ、呼びかけに反応しない:心停止
極端に速いもしくは遅い呼吸や、顎だけが動いて胸に空気が入っていないような呼吸は、特に注意が必要です。ケガ・病気のいずれの場合も、正常な呼吸をしていない場合や、呼びかけに応答がない場合は、すぐに119番に電話しましょう。
「救急車を呼んでもいいの?」
迷ったときは「救急相談センター」へ!

近年、軽症者の救急車利用が増えたことで、救急隊の到着が遅れる問題が発生しています。応急処置の開始が遅れると、それだけ救命の可能性は低くなってしまいます。緊急かどうか判断が難しい場合は、#7119(救急相談センター)などの相談窓口を活用しましょう。
なお、#7119以外の番号で救急電話相談などを行っている地域もあります。お住まいの地域の自治体のWEBサイトなどで番号を確認しておくと良いでしょう。
「応急手当講習会」受講のすすめ
救急隊が到着するまでに一般市民が応急手当を行うことで、命を救えることもあります。
消防署などでは「普通救命講習」が実施されており、心肺蘇生法やAEDの使い方、異物除去、止血法などを学ぶことができます。インターネットで受けられる「応急手当WEB講習」も活用すると良いでしょう。

まとめ
日常生活の中で起こりうるケガや不調に対して、応急手当の知識を身に付け、救急アイテムを備えておくことで、冷静に対処できるようになります。また、緊急時の判断力を高めるためにも、応急手当講習を積極的に受講しましょう。いざというとき、大切な人の命を救うことにつながります。
公開日:2025年4月23日
EM Alliance(Emergency Medicine Alliance)
ER型救急医療に関わる人々で構成される特定非営利活動法人(NPO法人)。2009年の発足以来、勉強会やミーティング開催、メーリングリストを通じた情報共有などを主な活動とし、現在では4,200名以上の会員と共に、日本の救急医療の発展と研修医の教育・研究活動への貢献を目指している。その他にも ER型救急医学に関する教育資料の提供、イベント情報の共有、業界情報の発信など、多岐にわたる活動を展開。 また、救急医療に関する悩みや相談に応じる「EMA for us」や、小児救急に特化した「EMA for kids」といった取り組みも行っている。本稿はEMA現代表である小林靖孟(2010年広島大学医学部卒業、MD/MBA、日本救急医学会救急科専門医)が担当した。