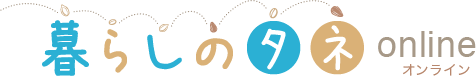季節の不調を解消!
<8月 食中毒>

高温多湿で食べ物が痛みやすくなるこの時期は、食品の取り扱いを少し油断しただけで「食中毒」を引き起こすリスクが高まります。食中毒とは、主に細菌やウイルスに汚染された食品や飲料を摂取することで、腹痛・下痢・嘔吐・発熱などの症状が現れる感染性疾患のこと。日常の食事やお弁当、外食など、私たちの身近なところに潜んでいます。このような季節性の不調の症状や原因、予防・対処法を専門の先生に教えてもらうこのシリーズ。今回は夏に多い「食中毒」の原因や予防法、万が一かかってしまったときの対処法について、専門の先生に伺いました。
まずはセルフチェック!
以下の症状に多く当てはまる場合、「食中毒」の可能性があります。

「食中毒」の原因と症状は?
夏場に発生しやすい「食中毒」。まずは、どんな原因があるのか、どんな症状が出るのかを知っておくことが、早期対応と重症化予防の第一歩です。
食中毒の主な原因
■細菌の繁殖
高温多湿な夏の環境は、細菌の繁殖にとって絶好の条件です。特に気温が30℃前後、湿度が70%以上になると、食材に付着した細菌はわずか数時間で大量に増殖します。原因菌としては、サルモネラ菌や腸炎ビブリオ、カンピロバクター、大腸菌(O157など)などが代表的で、十分な加熱がされていない肉や魚介類、冷蔵保存が不十分な食品を介して感染するケースが多く見られます。
■ウイルス感染
冬に流行しやすいノロウイルスですが、夏でも冷製料理や人からの接触によって感染・発症するケースがあります。また、サポウイルスやアストロウイルスなども、汚染された食品や飲料水を介して感染し、ノロウイルスと似た胃腸症状(嘔吐・下痢など)を引き起こすことがあります。
■調理・保存・衛生の不備(腐敗)
食中毒のリスクは、調理や保存、衛生管理の不備からも高まります。例えば、調理後の常温放置や加熱不足、まな板や包丁の使い回しなどが原因で、細菌やウイルスが食品に付着し繁殖します。特に生ものを扱う際は、調理器具の洗浄や手洗いなど基本的な衛生管理を徹底することが大切です。
【起こりやすい状況】
家庭や外出先などの食事環境でも起こるリスクがあります。特に時間をおいてから食べる食品は要注意。
例えば、炎天下での屋外レジャーやピクニックのお弁当は、保冷が不十分だと細菌が増殖しやすくなります。また、作り置き料理を長時間常温で保存していた場合も、食中毒のリスクが高まります。
さらに、手洗い不足の状態で調理・配膳を行ったり、まな板や包丁を使い回したりすることで、細菌やウイルスが食材に付着することも。外食でも、見た目や匂いに違和感があれば、無理に食べずに避けることが大切です。
日常のちょっとした油断が、思わぬ体調不良につながることもあるため、衛生管理と食品の取り扱いには細心の注意を図りましょう。

食中毒の症状
食中毒は、原因となる細菌やウイルスの種類によって症状が異なりますが、共通して現れやすい体の反応もあります。
<一般的な症状(共通)>
多くの食中毒に共通する代表的な症状は、以下の通りです。
・吐き気、嘔吐
・腹痛
・下痢(水様便、粘液便など)
・発熱(微熱~38℃程度の高熱)
<細菌性食中毒に多い症状>
細菌による食中毒は、急性で重い症状が出やすいのが特徴です。
・急激な腹痛と下痢
・発熱(38~40℃程度の高熱)と嘔吐
<ウイルス性食中毒に多い症状>
ウイルスによる食中毒は、比較的軽症で済むこともありますが、感染力が非常に強く、集団感染につながるケースもあります。
・嘔吐(回数が多い)
・水下痢(水のように液状に近い)
・発熱はない、もしくは微熱程度
<注意が必要な症状>
以下のような症状が見られる場合は、早急に医療機関を受診することが大切です。
・血便、強い脱水症状(口の渇き、尿が出ない)
・高熱が長引く
・乳幼児や高齢者の急激な体調悪化
【食中毒と症状の違い】
食中毒の症状は、細菌やウイルスによって異なり、また風邪の症状にも似ているため判断がつきにくいことがあります。症状の現れ方や、「何を食べたか」「同じものを食べた人が発症しているか」といった背景に注目することで、食中毒を早期に疑い、適切な対処につなげる手掛かりとなります。
| 原因 | 潜伏期間の目安 | 発生しやすい食品、環境 | 症状 | |
|---|---|---|---|---|
| 細菌性 | サルモネラ菌 | 約6~72時間 | 卵・鶏肉など | 吐き気・発熱・下痢・腹痛など |
| 腸炎ビブリオ | 約4~24時間 | 生の魚や貝など | 激しい腹痛や下痢 | |
| カンピロバクター | 約2~5日 | 生や加熱不足の 鶏肉 |
発熱、腹痛、下痢が長引く傾向 | |
| 大腸菌 (O157など) |
約1~10日 (平均3~5日) |
生や加熱不足の 牛肉など |
激しい腹痛、げり、血便 重症化しやすく、腎障害や重篤な合併症を引き起こすことも |
|
| 手指の不衛生・腐敗(黄色ブドウ球菌など) | 約1~6時間 | 弁当、作り置き料理・常温放置など | 吐き気・嘔吐中心 | |
| ウイルス性 | ノロウイルス | 約12~48時間 | 生牡蠣などの二枚貝 (汚染された手で調理した)非加熱食品 |
嘔吐・下痢・感染力が強い 幅広い年齢層で感染 |
| サポウイルス | 約1~3日 | 生牡蠣などの二枚貝 (汚染された水で洗った)食品など |
嘔吐・下痢 乳幼児の感染が多い |
|
| アストロウイルス | 約1~4日 | (十分に洗浄されていない)生野菜、カットフルーツなど | 軽い胃腸症状が中心。 乳幼児や高齢者の感染が多い |

~先生からのアドバイス~
「食中毒」の予防と対処法

食中毒を防ぐためには、日ごろの食生活や衛生管理が重要です。特に夏は高温多湿の環境が細菌やウイルスにとって好条件となるため、調理や保存にも注意しましょう。
■手洗いの徹底
調理前、食事の前、生肉や魚介類を扱った後は、石けんと流水でしっかり手を洗いましょう。手指を清潔に保つことが感染予防の基本です。
■加熱と冷却の管理
調理の際は、肉や魚の中心までしっかり加熱し、作り置き料理は早めに冷蔵保存を。食べる前には再加熱を忘れずに行いましょう。
■調理器具の衛生管理
まな板や包丁は生もの用と加熱用で使い分け、使用後は洗剤でよく洗い、定期的に消毒することが大切です。
■持ち歩く食品にも注意
お弁当や外出時の食品は、保冷剤を使用し、長時間持ち歩かないようにしましょう。とくに炎天下ではリスクが高まります。
■安静と水分補給
食中毒にかかった場合は、無理をせずに安静を保ち、水やお茶でこまめに水分補給を行いましょう。下痢止めの使用は、原因物質を体外に排出しきってからが望ましいとされています。
■脱水対策
下痢や嘔吐が続く場合は、経口補水液(OS-1など)や、薄めたスポーツドリンクで失われた水分と電解質を補給します。
■自己判断で薬を使わない
症状が長引いたり、発熱や血便が見られたりする場合は、自己判断で薬を使わず、早めに医療機関を受診しましょう。

「食中毒」まとめ
食中毒は、かかってからの対処よりも、予防が何よりも大切です。特に夏場は細菌やウイルスが繁殖しやすいため、調理時の加熱や保存方法、調理器具の衛生管理などを徹底することが重要です。また、少しでも体調に違和感があれば、早めに体を休め、水分補給を行うなど、迅速な対処を心がけましょう。症状が重かったり長引いたりする場合は、自己判断せず、医師の診断を受けることが安心・安全につながります。正しい知識と予防を味方につけて、安心で快適な夏の食卓を楽しみましょう。
※この記事内容は、執筆時点2025年8月6日のものです。
 森 勇磨(もり ゆうま)
森 勇磨(もり ゆうま)
ウチカラクリニック代表・Preventive Room株式会社代表・産業医・内科医・労働衛生コンサルタント
東海高校・神戸大学医学部医学科卒業。研修後、藤田医科大学病院の救急総合内科にて救命救急・病棟で勤務。救急現場での経験から、「病院の外」での正しい医療情報発信に対する社会課題を痛感し、YouTubeでの情報発信を決意。2020 年2月より「予防医学 ch/ 医師監修」をスタートし、現在チャンネル登録者は42万人を突破し、総再生回数は4000万回を超える。株式会社リコーの専属産業医として、予防医学の実践を経験後、独立。産業医としての「企業と人を健康にする予防医学」、さらには「従来の枠組みにとらわれず、病院の外でできるあらゆる予防医学」のアプローチに挑戦して、1人でも後悔する人を減らしたいという思いから、Preventive Room 株式会社を立ち上げる。現在はオンライン診療に完全対応したクリニック「ウチカラクリニック」を通じて、オンライン診療の適切な形での社会実装、セルフケアの推進に取り組んでいる。
https://uchikara-clinic.com/