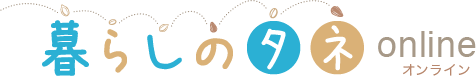気付いたころには回復しない!!
イヤホン難聴のリスク

難聴というと高齢の方のイメージがあるかもしれませんが、最近では、イヤホンやヘッドホンで音楽などを大きい音で聴くことによる難聴の危険が叫ばれるようになりました。そのイヤホン難聴(※)の危険性と予防法をご紹介します。 ※正式名称は「ヘッドホン・イヤホン難聴」
世界11億人が抱える
耳が聞こえなくなる危険性
難聴には、老化や病気など、様々な原因がありますが、イヤホン難聴は音を感じ取る内耳がダメージを受けることで発症します。イヤホンで大音量で聞き続けると、音のエネルギーが拡散せずに内耳に伝わるため、内耳が大きなダメージを受けます。そのダメージが数カ月から数年と、ゆっくり蓄積していき、やがてイヤホン難聴が発症してしまうのです。ここ数年で、音楽を聴いたり、動画を見たり、オンライン会議をしたりと、イヤホンをする機会が増加。世界11億人(※1)がその発症のリスクを抱えているとされています。
初期症状は、聞こえづらさや耳鳴り、耳閉感(耳が詰まった感じ)です。イヤホン難聴は一度発症したら二度と回復することがないため、予防することが大切です。もし、このような症状を感じたら、すぐに耳鼻科を受診しましょう。
発症のリスクは、音量の大きさと使用時間の長さで高まります(※2)。一つの基準として、成人なら「80dBで1週間40時間」、子どもなら「75dBで1週間40時間」を越えないようにするのが良いとされています 。この基準と下記を参考に予防を心掛けていきましょう。
※1 世界保健機構(WHO)(2019年)による。
※2 音に対する耐性には個人差もあります。

イヤホン難聴の予防法
● 音量を上げ過ぎない
音量が大きいほど音のエネルギーも大きくなるため、内耳がダメージを受けやすくなります。音量の目安は近くの人の会話が聞き取れる程度が良いとされています。

● 長時間聴かない
1時間に1回、10分程度はイヤホンを外して耳を休ませるのがおすすめです。
●ノイズキャンセリング機能を使う
周囲の雑音を抑えるノイズキャンセリング機能を使えば、音量を上げ過ぎずに済みます。こういった機能を活用するのもおすすめです。
※この記事内容は、執筆時点2024年6月30日のものです。
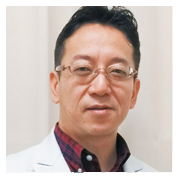 松延 毅(まつのぶ・たけし)
松延 毅(まつのぶ・たけし)
慶應義塾大学卒。医学博士。耳鼻咽喉科・頭頸部外科専門医。日本医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科准教授。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会ヘッドホン・イヤホン難聴対策WG 委員長。