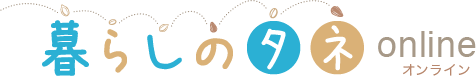人生100年時代の「脳活」習慣
第2回 生活の中で脳を活性化させよう

高齢化社会で大きな課題となっている「認知症」ですが、脳機能は40代から少しずつ低下し始めます。認知症を予防するためには、若いうちから脳に良い活動「脳活」を習慣付けることが大切です。『人生100年時代の「脳活」習慣』第2回は、脳の活性化で欠かせない食事・運動・睡眠をはじめ、脳に刺激を与える活動を紹介します。
「健康な脳」で認知症を予防
認知症を防ぐために大切なのは「健康な脳」を維持すること。それには「栄養バランスの取れた食事」「適度な運動」「良質な睡眠」が必要です。認知症は進行性の病気であり、一度発症してしまうと完全に治すことはできません。今のうちから生活習慣を見直していきましょう。

■健康な脳を維持するための食事
脳の健康を維持し、神経細胞の働きを支えるためには、栄養バランスの取れた食事が大事です。脳機能を高める栄養素を意識して積極的に取ってみてください。
・たんぱく質:魚や豆類、卵、肉などに多く含まれ、脳の成長や機能維持を助けます。
・食物繊維:葉物野菜やきのこ類、海藻などに多く含まれ、腸内環境を整え、認知機能を向上させます。
・ビタミンB群:脳神経の活動をサポートします。シジミやアサリ、イクラ、煮干し、ほうれん草、焼きのり、牛レバーなどに多く含まれています。
・ビタミンD:セロトニンの分泌が促進され、気持ちの落ち込みを防ぐのに役立ちます。サケ、イワシなどの魚、卵黄、干しシイタケ、キクラゲなどに含まれています。
■効率よく栄養が取れる「地中海食」「和食」がおすすめ!
上記の栄養素を効率的に摂取できる食事として、「地中海食」と「和食」が推奨されています。
地中海食は、ブイヤベースやパエリアなど、地中海沿岸地域(イタリアやスペイン、ギリシャなど)の伝統的な食事スタイル。野菜や魚介類、穀類などに加え、抗酸化物質を含むオリーブオイルやナッツなどを使った料理が多く、脳細胞へのダメージを防ぎ、老化予防にも役立つとされています。
また、和食も、青魚や大豆、野菜、腸内環境を整える発酵食品、抗酸化物質が豊富な海藻など、脳機能に必要な栄養素を含む食材が多く使われています。
地中海食
・オリーブオイル:不飽和脂肪酸を多く含み、抗酸化作用が強い。
・魚介類、ナッツ、果物、野菜、全粒穀物:抗酸化物質や、認知機能の低下を低減する「オメガ3脂肪酸」が豊富。
・青魚:DHA・EPAが血中の中性脂肪や悪玉コレステロールを減らし、動脈硬化や脳血管性認知症の予防に。

和食
・豆腐や納豆:大豆食品に含まれる「レシチン」は血中コレステロールや中性脂肪を低下させる働き。
・発酵食品:善玉菌を多く含む発酵食品は腸内環境を整え、脳の働きをサポート。
・海藻類:ミネラル、ビタミン類、食物繊維が豊富で肥満予防や、海草類に含まれる「アラキドン酸」が脳の神経細胞の生成に役立つ。
さらに、白米を玄米にすると食物繊維がプラス。ただし、和食は塩分が多くなりがちなため、“塩分控えめ”を心掛けましょう。

■健康な脳を維持するための運動
適度な運動は脳の血流を改善し、神経の働きの活性化、ストレス軽減や睡眠の質向上にも役立ちます。脳に良い運動として、ウォーキングやジョギング、水泳などの「有酸素運動」と、スクワットやかかと上げなどの「筋トレ」の2つをご紹介します。少し息が上がる程度の運動をするとより効果的です。
有酸素運動
ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、血流を促進し、脳への酸素供給を増やします。
【運動例】
・ウォーキング:背筋を伸ばし、肩の力を抜いて自然に腕を振るようにして、歩幅はやや大きめに。かかとから着地し、つま先から蹴り出すように歩きます。坂道や公園のアップダウンを取り入れると効果的です。
・ジョギング:背筋を伸ばし、肩の力を抜いてやや前傾姿勢を保ちながら、腕を90度に曲げて自然に振るようにして走りましょう。歩幅は無理に広げず、自然な幅で。
・水泳:泳法はなんでもOK。速くなくてもいいので、同じペースを保ちながら泳ぐようにしましょう。泳ぐ前後にストレッチをして筋肉や関節を伸ばし柔軟性を高めておくことで、よりスムーズに泳げます。
【頻度・時間の目安】
・認知機能低下の予防:週に3回、1日30分程度
・認知機能の向上:週4回、1回60分程度

筋トレ
スクワットやかかと上げ、ダンベルを使ったトレーニングなどで筋力を鍛えることで、脳の神経細胞の活性化が期待できます。
【運動例】
・スクワット:足を肩幅よりやや広めに開き、つま先をやや外側に向けます。手を胸の前で軽く組み、お尻を後ろに突き出して、太ももと床が平行になるようにしゃがみます。かかとで床を押すようにしてゆっくりと元の位置に戻ります。
・かかと上げ:足を肩幅に開き、つま先と膝が同じ向きになるように立ち、必要であれば壁などにつかまりバランスを取ります。息を吸いながらゆっくりとかかとを上げ、息を吐きながらゆっくりと下げるふくらはぎに効いていることを意識しながら繰り返しましょう。
【頻度・時間の目安】
週に3回、10〜15回を1セットとして3セット程度

体×頭を動かして効果アップ
体だけでなく頭も同時に使うと、さらに脳が活性化します。
【体×頭を動かす運動例】
・九九を唱えながら歩く
・47都道府県名を挙げながら歩く
・複雑な動きを伴うダンスや太極拳など

■健康な脳を維持するための睡眠
良質な睡眠は、記憶の定着や脳の回復に欠かせません。睡眠時間は7時間を目安に確保することが理想的です。

【質の良い睡眠のために気を付けたいこと】
・朝起きたらまず太陽の光を浴びて、体内時計を整える
・寝る3時間前は何も食べない
良く眠れない場合は、まず原因の解消
睡眠の質が悪い場合、頻尿や睡眠時無呼吸症候群などの原因も考えられるため、医療機関を受診して適切に対処しましょう。

日常に取り入れたい「脳活」習慣
食事・運動・睡眠以外にも、日々の中で脳を刺激する活動を積極的に行いましょう。
■家事で脳活
料理など手先を使ったり、効率的な作業の順番を考えたりすることで脳を使います。また、掃除など作業に集中することでマインドフルネス(瞑想)のようにストレス解消につながり、脳にとってプラスに働きます。

■芸術的な趣味で脳活
芸術活動は普段使わない脳の領域を刺激し、認知機能の向上につながります。歌う、楽器を演奏する、絵を描く、外国語を学ぶなど。また、新しいことにチャレンジすると、脳の神経ネットワークが活性化されていきます。

■コミュニケーションで脳活
人との交流は、脳を活性化させます。孤独は認知症のリスクを高めるため、積極的に人と関わることを意識しましょう。家族や友達との会話、趣味サークルへの参加やボランティア活動などを通じてコミュニケーションの機会を増やすのもおすすめです。

健康な脳のためにはストレスを蓄積させない
過度なストレスは脳の働きを低下させる原因になります。日々のストレスはこまめに解消することも大切です。
【脳へのストレスを軽減する方法】
・スマートフォンやパソコンの使いすぎを避け、脳を酷使しないように
・マインドフルネス(瞑想)を取り入れる

まとめ
「脳活」の基本は、規則正しくメリハリのある生活を送ること。食事・運動・睡眠を整えることは心身の健康維持にもつながります。人生100年時代を元気に過ごすために、脳を活性化させる生活をぜひ始めましょう。
公開日:2025年4月30日
 今野 裕之(こんの ひろゆき)
今野 裕之(こんの ひろゆき)
医療法人社団TLC医療会ブレインケアクリニック名誉院長。一般社団法人日本ブレインケア・認知症予防研究所代表理事・所長。日本初のリコード法(アルツハイマー病の画期的治療プログラム)認定医。認知症の予防・治療に栄養療法やリコード法を取り入れ、一人ひとりの患者に合わせた診療に当たっている。著書に『最新栄養医学でわかった! ボケない人の最強の食事術』(青春出版社)、『ボケたくなければ「寝る前3時間は食べない」から始めよう 認知症診療医に教わる最強の生活習慣』(世界文化社)がある。その他、監修多数。