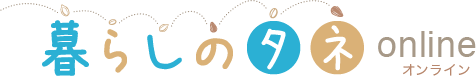がん予防は「食事」と「筋トレ」から始めよう!
第1回 がんに負けない体をつくる「食事」

がんは遺伝よりも「生活習慣」による影響が大きいといわれています。カギを握るのは“腸内環境”と“筋肉”。この記事では全2回にわたり、「がんに負けない体のつくり方」を、食事と運動の両面からご紹介します。第1回は、免疫の土台をつくる“腸内環境を整える食事”編です。
がんの発症メカニズム
がんの原因となる「がん細胞」は、普通の細胞が変異して、異常に増殖するようになったものです。本来であれば、体の中にある免疫細胞によってがん細胞は排除されます。

ところが、ストレスや加齢、生活習慣の乱れなどで免疫細胞の働きが弱まると、がん細胞を処理し切れない状態に。がんは、検診で発見される頃には直径1cmほどですが、そこまで成長するのに約10年かかるといわれています。つまり、その間ずっと免疫細胞の機能が低下している状態が続いているということです。
がん予防のカギは「腸内環境」
免疫細胞の約70%は腸に存在しているとされ、腸内環境の乱れ=免疫の乱れといっても過言ではありません。特に大腸がんをはじめ、腸内環境との関係が深いがんは多く、「腸を整えること」はがん予防の第一歩といえるのです。

がんリスクを高めてしまう食品を知ろう
腸内環境に悪影響を与える食品は、できるだけ避けたいもの。中でも注意が必要なのが、糖分・塩分・脂肪を多く含み、保存料や着色料、香料などの添加物を加えて作られた「超加工食品」と呼ばれるものです。こうした食品を常食すると腸内環境が乱れ、がんのリスクが高まることが報告されています。
【がんリスクを高める超加工食品】
・インスタント食品
・スナック菓子
・カップ麺
・菓子パン
・清涼飲料・炭酸飲料など

加工肉(ハム・ソーセージなど)やアルコール、乳製品の摂り過ぎにも注意が必要です。完全に避けるのは難しいため、「週の半分は自炊する」「加工肉は週1回まで」など、頻度と量を意識して調整しましょう。
子どもの食事にも注意を
子どもはスナック菓子や清涼飲料水、加工肉などを好みがちです。成長期の腸内環境はまだ不安定で、加工食品の摂取が続くと、将来の肥満や生活習慣病のリスクにもつながります。忙しい日も多いですが、できるだけ自然由来の食品を選ぶようにしましょう。

とはいえ、加工食品を“ゼロ”にするのは難しいもの。ポイントは、「頻度」と「量」を控えること。「お菓子は週末だけ」など、家族でルールを決めてメリハリをつけると続けやすくなります。
がんリスクを下げる食品を摂ろう
がんの発症を遠ざけるには、「悪いものを減らす」と同時に、「良いものを積極的に摂る」ことも大切です。腸が喜ぶ食品を取り入れることで、腸内環境が整い、免疫機能が自然と高まっていきます。
■腸内細菌のエサになる食物繊維
腸内細菌が正常に働くためには“エサ”が必要で、その代表が食物繊維です。食物繊維が腸内で発酵されることで「短鎖脂肪酸」という物質が生まれ、腸の炎症を抑えたり、免疫細胞の働きをサポートします。食物繊維には水溶性と不溶性があり、この2種類をバランス良く摂ることが理想的です。
・水溶性食物繊維:海藻・果物・ごぼう・里芋など

・不溶性食物繊維:野菜・豆類・きのこ・穀物など

朝食に果物、昼や夜に野菜スープやきのこ炒めを加えるだけでも、腸内環境の改善につながります。
■腸にとって良い菌を含む発酵食品
納豆や味噌、ぬか漬けやキムチなどの発酵食品は腸にとって良い菌を含み、腸内環境を整えます。ただし、塩分の摂り過ぎには注意が必要です。漬物などは「小鉢一皿程度」を目安に。塩分が気になる場合は減塩タイプや具だくさん味噌汁にして薄味にすると良いでしょう。

■きのこ・海藻類で免疫をサポート
きのこや海藻類には、免疫細胞の働きを活性化させる成分が含まれています。特に、きのこに含まれるβ-グルカンは免疫細胞を刺激し、がん細胞への抵抗力を高めるといわれています。わかめやひじきなどの海藻は、腸の動きを助けるだけでなく、ミネラル補給にも役立ちます。
■抗酸化成分を含む“カラフル食材”を
細胞の酸化(=老化やがんの原因)を防ぐために欠かせないのが、ポリフェノールやカロテノイドなどの抗酸化成分。「赤・黄・緑などの野菜や果物」に豊富に含まれています。
食卓をカラフルに、“虹を食べる”ように食材を選びましょう。

食べ方・タイミングの工夫も大切
食事内容だけでなく、食べ方も腸の健康に影響します。
■腹8分目にする
食べ過ぎは腸の負担や血糖値の急上昇につながります。「少し足りないかな」くらいがちょうどいいと考えましょう。腹8分目にすることで消化がスムーズになり、腸の働きも安定。結果的に、免疫機能や代謝の維持にも役立ちます。よく噛んでゆっくり味わうこともポイントです。

■「食べない時間」をつくる
腸には、食べたものを消化・吸収した後に「休む時間」が必要です。食べ続けていると、腸の働きがオーバーワークになり、腸内環境が乱れやすくなります。間食を減らし、腸をしっかり休ませましょう。

■就寝の2〜3時間前には飲食を終える
夜遅い食事は、腸に大きな負担となります。寝ている間にも消化活動が続くと、腸が休めず、翌朝の胃もたれや便秘の原因にもなります。理想は、就寝の2〜3時間前に食事を終えること。どうしても夕食が遅くなる日は、軽めのメニューにしたり、汁物や温野菜など消化の良いものを選ぶ工夫をしましょう。
■体の状態は便通でチェック
食事や食べ方が自分に合っているかどうかは、便通が教えてくれます。日々の排便リズムや便の状態を“腸からのサイン”として毎日チェックすることも大切です。
まとめ
私たちの体は、毎日の食事でつくられています。質の良い食事で腸を整え、免疫を守り、がんを遠ざける。理想は分かっていても、毎日すべてを実践するのは難しいかもしれません。大切なのは、「週のうち何回かでも腸が喜ぶ食事をする」意識。無理をせず、できることから少しずつ。小さな積み重ねが、がんを遠ざける大きな力になります。
次回は、もう一つのがん予防の柱である「筋肉」に注目し、運動によって“がんに負けない体”をつくる方法を紹介します。
※この記事内容は、執筆時点2025年11月19日のものです。
 石黒 成治(いしぐろ せいじ)
石黒 成治(いしぐろ せいじ)
消化器外科医、ヘルスコーチ。国立がんセンター中央病院で大腸癌外科治療のトレーニングを受け、名古屋大学医学部附属病院、愛知県がんセンター中央病院、愛知医科大学病院に勤務。
2018年から予防医療を行うヘルスコーチとして活動。著書に『専門医が教える がんにならない食事法』『筋肉が がんを防ぐ。 専門医式 1日2分の「貯筋習慣」』(KADOKAWA)などがある。