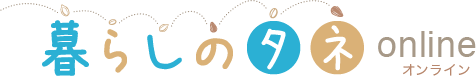季節の不調を解消!
<7月 夏かぜ>

毎年の猛暑で体調を崩す人が増えています。中でも「夏かぜ」は免疫力が落ちやすい時期に流行し、重症化することもあります。このような季節性の不調の症状や原因、予防・対処法を専門の先生に教えてもらうこのシリーズ。今回は、夏かぜの症状や原因、予防・対処法について専門の先生に伺いました。
まずはセルフチェック!
以下の症状に多く当てはまる場合、「夏かぜ」の傾向があります。

「夏かぜ」の原因と症状は?
夏かぜとは、主にウイルス感染によって引き起こされます。代表的なウイルスには、エンテロウイルスやコクサッキーウイルス、アデノウイルスなどがあり、これらが原因で、手足口病、ヘルパンギーナ、プール熱(咽頭結膜熱)などの病気が発症することもあります。
これらのウイルスは、湿度が高く、気温が上昇する季節に活発になるため、梅雨から夏にかけて感染が広がりやすくなります。また、夏は冷房が効いた室内と外の気温差が激しく、体温調整が難しくなるほか、発汗や脱水によって免疫力が低下し、風邪を引きやすくなる状態になりがちです。さらに、イベントや旅行など、人が集まる機会が増えるため、接触を通じた感染拡大が起こりやすくなります。
夏かぜの症状は、通常の風邪に似ていますが、いくつか特徴的な点があります。まず、原因となるウイルスは、喉や腸で増殖しやすいため、喉の痛みや違和感、咳、腹痛、下痢、嘔吐などの症状が出やすくなります。一方で、冬かぜに多い鼻水や鼻づまりといった鼻の症状はあまり見られません。
また、体温調節機能の乱れや脱水を伴うことがあり、暑くても汗が出にくかったり、体が熱っぽく感じたりすることもあります。発熱はウイルスの種類によって異なり、突然38℃以上の高熱が出る場合もあれば、37℃台の微熱が数日続くこともあります。
一般的な風邪に比べて長引く傾向があり、熱が下がってからもだるさや疲労感、食欲不振が続くことがあります。多くの場合は1週間程度で回復しますが、免疫力が低い人や高齢者、子どもなどは症状が重くなることもあるため、注意が必要です。

一般的な風邪(冬かぜ)との違い
| 夏かぜ | 一般的な 風邪(冬かぜ) |
|
|---|---|---|
| 発症時期 | 梅雨〜夏 | 秋〜春 |
| 原因となる 主なウイルス |
エンテロウイルス、 アデノウイルス、 コクサッキーウイルスなど |
ライノウイルス、 コロナウイルス、 RSウイルスなど |
| 感染が引き起こす病気 | 手足口病、 ヘルパンギーナ、 プール熱など |
インフルエンザ、 急性上気道炎、 気管支炎など |
| 発熱 | ウイルスの種類によって微熱または高熱が出る | 高熱が出る |
| 症状 | 喉の痛み、咳、 腹痛、下痢、嘔吐、 粘り気のある鼻水など |
鼻水、鼻づまり、咳など |
| 発症しやすい環境 | 高温多湿、 室内外の温度差、 脱水など |
乾燥、寒冷、 換気不足など |
| 感染経路 | 接触感染・飛沫感染 (タオル・プールなど) |
飛沫感染・接触感染 (くしゃみ・咳) |
~先生からのアドバイス~
「夏かぜ」の予防と対処法

■こまめな水分補給
発熱や汗で失われた水分を補うために、適切な水分補給を行いましょう。また、脱水症状を避けるために、塩分を含んだ飲み物を摂ることも有効です。
■十分な睡眠と休息
免疫力を高めるためには、規則正しい生活と十分な睡眠が不可欠です。暑さで寝苦しい夜もありますが、体調管理のためには休息が重要です。また、無理に仕事や外出をせず、しっかり休むことが回復を早めます。体を温めて安静に過ごしましょう。
■室内の温度管理
外気と室内の温度差が大きくなると、体温調整が難しくなり、免疫力が低下します。エアコンの温度設定は、 26〜28℃を目安に設定し、直接冷風が当たらないよう工夫しましょう。外との温度差が大きいときは、薄手の羽織りものや靴下などで体を冷やしすぎないよう対策することも効果的です。
■手洗いやうがいの徹底
外出先から帰宅後は必ず手洗いとうがいを行い、ウイルスの侵入を防ぎます。特に人が多く集まる場所に出かけた後は、こまめな手洗いを行いましょう。
■抵抗力を高める食事
バランスの取れた食事で免疫力を保つことが大切。特に、夏に不足しがちになるビタミンCを野菜や果物から摂ったり、体の組織をつくるたんぱく質を肉・魚・豆類などからしっかり摂ったりすることで、免疫力をあげ、体の抵抗力を高められます。冷たいものの摂りすぎは胃腸の働きを弱めるため、暑い時期であっても温かい食事や消化の良いメニューを意識しましょう。
■医師の診断を受ける
もし症状が長引いたり、熱が高くなったり、体調が急激に悪化する場合は、早めに医師に相談しましょう。特に、高齢者や子どもは重症化する可能性があるため、注意が必要です。

「夏かぜ」まとめ
夏かぜは、梅雨ごろから夏にかけてに流行する風邪で、冬に多い風邪とは性質が異なります。主な原因はエンテロウイルスやアデノウイルスなどで、特に高温多湿な環境で繁殖しやすく、のどの痛みや発熱、下痢などさまざまな症状を引き起こします。
予防には、こまめな水分補給やバランスの取れた食事、そして十分な睡眠が欠かせません。こうした日頃の健康管理によって免疫力を高めておくことが、夏かぜにかかりにくくするポイントです。
また、もし体調の変化を感じたら、無理をせず早めに休養を取ったり、医療機関を受診したりすることで、症状が軽いうちに回復しやすくなります。夏を元気に乗り切るためにも、日頃からしっかりと体調を整えておきましょう。
※この記事内容は、執筆時点2025年7月9日のものです。
 森 勇磨(もり ゆうま)
森 勇磨(もり ゆうま)
ウチカラクリニック代表・Preventive Room株式会社代表・産業医・内科医・労働衛生コンサルタント
東海高校・神戸大学医学部医学科卒業。研修後、藤田医科大学病院の救急総合内科にて救命救急・病棟で勤務。救急現場での経験から、「病院の外」での正しい医療情報発信に対する社会課題を痛感し、YouTubeでの情報発信を決意。2020 年2月より「予防医学 ch/ 医師監修」をスタートし、現在チャンネル登録者は42万人を突破し、総再生回数は4000万回を超える。株式会社リコーの専属産業医として、予防医学の実践を経験後、独立。産業医としての「企業と人を健康にする予防医学」、さらには「従来の枠組みにとらわれず、病院の外でできるあらゆる予防医学」のアプローチに挑戦して、1人でも後悔する人を減らしたいという思いから、Preventive Room 株式会社を立ち上げる。現在はオンライン診療に完全対応したクリニック「ウチカラクリニック」を通じて、オンライン診療の適切な形での社会実装、セルフケアの推進に取り組んでいる。
https://uchikara-clinic.com/