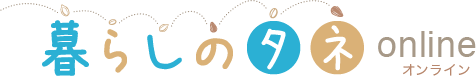今からでも遅くない!正しい腸活
第1回 専門家が教える腸内環境の整え方

最近、耳にすることの多い「腸活」。実際にやってみようと、ヨーグルトなどの「腸に良い」とされる食品ばかりを食べ続けていませんか?「ばっかり食べ」は実は腸に良くありません。間違った腸活は、かえって体の調子を悪くすることもあるのです。この記事では、正しい腸活について、全2回にわたり専門家に教えていただきます。第1回目は「腸内環境の整え方」です。
「腸活」とは?
知っておきたい腸の役割
「腸活」とは、腸内環境を整える活動です。
では、そもそもなぜ腸活が必要なのでしょう? それは、腸が人間にとって重要な役割を担っているからです。食べ物を消化や吸収する働きに加えて、悪い菌から体を守る免疫器官としても働き、さらにはメンタルにも腸は影響しています。
腸の役割①食べ物の消化器官

消化器官が腸の基本となる役割です。腸は小腸と大腸の大きく二つに分かれ、小腸は胃で消化された食べ物をさらに分解して栄養素を吸収します。大腸は小腸で吸収されずに残った物から水分やミネラルを吸収して便を作り体の外へ排出できるようにします。
腸の役割②悪い菌から体を守る免疫器官

体に入ってくるのは良いものだけでなく、食中毒を起こす細菌など悪いものの可能性があります。そこで必要になるのが免疫器官としての役割です。腸には体の半分以上の免疫細胞が集まり、体内に有害なものの侵入を防ぎます。さらに腸内の免疫細胞は動いて体全体の免疫機能に働きかけ、何を退治し・何を吸収するかの教育も行っているのです。「花粉症には腸活が良い」といわれるのも、腸で教育を受けた免疫細胞が鼻に移動して働くからです。
「免疫力」と聞くと「高いほど良い」と思われがちですが、実は高まりすぎても良くありません。免疫力が高すぎると暴走状態になり、体に良いものまで退治してしまいます。
その例が「顔のシワ」です。免疫力が高まりすぎるとコラーゲンを壊したり、正常な細胞を壊してしまい、シワが深くなってしまいます。

また、糖尿病や動脈硬化なども免疫の暴走が要因であることが最近の研究で分かってきました。
免疫は「整える」ことが大切です。
腸の役割③メンタルコントロール

「緊張でおなかが痛くなる」経験をされた方も多いのではないでしょうか。腸は脳に次ぐ多さの神経細胞が集まり、ストレスが腸に伝わることでおなかを下すなどの影響が出ます。逆に、腸から脳へも働き、腸内環境の乱れが脳に伝わって不安を感じるなど、メンタルの症状として表れることも分かってきました。
健康的な腸のための正しい腸活
健康的な体・健全なメンタルのためには、健康的な腸であることが大切です。腸活で目指す「整った腸内環境」は、腸内の菌の多様性が保たれ、連携が機能している状態。
例えば、下の図のように第1~3ステップでいろいろな菌が機能することで、短鎖脂肪酸として知られる酢酸・酪酸・プロピオン酸などが生成され、「腸のエネルギーになる」「免疫を整える」「悪い菌を減らす」働きをしてくれます。

この連携を機能させるためには、「①菌のエサを摂る」「②腸活に必要な菌を摂る」「③菌の正常な働きを促す栄養素を摂る」という食事の3つのポイントがあります。
■腸活を促す食事の3つのポイント
①菌のエサを摂る
菌にはエサが必要で、不足すると腸内の粘膜など体に必要なものまで食べてしまいます。エサとなるのは「発酵性食物繊維」と「難消化性オリゴ糖」です。
・発酵性食物繊維を含む食品:こんにゃく、昆布、タマネギ、ゴボウ、ブロッコリー、リンゴ、キウイ、玄米など
・難消化性オリゴ糖を含む食品:タマネギ、ゴボウ、バナナ、大豆、牛乳など

食物繊維・オリゴ糖以外でエサになるのは「難消化性でんぷん」です。含まれるのは、玄米など精製度の低いもの、そして冷めたごはん。熱々のごはんは「消化性でんぷん」で糖として吸収されますが、冷めることで消化されにくいでんぷんとなり、菌の良いエサとなります。おにぎりやお弁当を食べる際、温めずにそのまま食べるのがおすすめです。

食物繊維とは
人の消化酵素では消化できない食品中の成分の総称で、「水溶性」「不溶性」「発酵性」などの種類があり、同じ食品に複数含まれている場合もあります。特に発酵性が腸内細菌のエサとなり、私たちの体にとって良い働きをしてくれる短鎖脂肪酸になりやすいです。
オリゴ糖とは
少数の糖が結合したもの。「消化性」と「難消化性」があり、難消化性が腸内細菌まで届きます。
②腸活に必要な菌を摂る
菌のエサとして食物繊維やオリゴ糖が体内に入っても、分解する菌がいないと腸内環境は整いません。そこで必要になるのが「納豆菌」「乳酸菌」「ビフィズス菌」などの菌です。体内に残るのは数日のため、コンスタントに食べるようにしましょう。
・腸活に必要な菌を含む食品:納豆(納豆菌)、ヨーグルト(乳酸菌やビフィズス菌)、味噌(乳酸菌)などの発酵食品

このとき注意したいのが、「ばっかり食べ」です。納豆やヨーグルトは、種類によって含まれる菌が異なります。ヨーグルトであれば「乳酸菌」「ビフィズス菌」などがあり、どれか一つばかりを食べてしまうと、菌の連携のバランスが崩れてしまう危険性があります。いろんな種類を食べるのがおすすめです。
③菌の働きを促す食品を食べる
菌の働きを促すためには、ビタミンB1が必要になります。
・ビタミンB1を含む食品:大豆、豚肉、ウナギ、玄米など

特に大豆食品である納豆は納豆菌とビタミンB1が摂れます。また、ビタミンB1はタマネギやニンニクと一緒に食べると吸収されやすくなるので、豚肉のタマネギ炒めなどがおすすめです。
水分補給を忘れずに!
上記の栄養素が腸には必要ですが、水分も大切です。水分を補給することで菌や細胞が正常に動けるようになり、体内に水分が入ってくることで腸が動き出す合図にもなります。
最後に、腸活に関する疑問に専門家に答えていただきました。
■腸活Q&A
Q.腸活にサプリメントは使ってもいいですか?
A.必要な栄養素を補給できないときはサプリメントも活用ください
上記で挙げたような食品を食べられていない、食欲がなくて食べられないような場合、サプリメントで補うのは問題ありません。ただし、基本は、食事からしっかり栄養素を摂ることです。また、サプリメントによっては摂り過ぎのリスクもあるので、用法・用量をきちんと守ってくださいね!

Q.ヨーグルトは夜に食べたほうが良いと聞いたのですが…
A.朝昼晩にこだわらなくてOKですが、すきっ腹では食べないように
菌は体内に数日は残っているので、夜にこだわらなくても大丈夫です。ただ、すきっ腹では胃酸が強すぎて、良い菌が腸まで届きにくくなってしまいます。ヨーグルトは食後に摂るのが良さそうです。

Q.菌は熱に弱い?
A.熱すぎると菌は死んでしまう可能性あり
「味噌汁を作るときは、火を止めてから味噌を入れる」と聞いたことがあるかと思います。死滅する温度は菌によりますが、煮立たせたり、沸騰している中に入れるのは避けましょう。

Q.運動や睡眠も腸活には必要ですか?
A.おなかを動かす運動、しっかり睡眠をとることで腸はさらに元気に!
運動ではおなか(腸)を物理的に動かすのが良く、おすすめは腹筋です。ストレッチやウォーキングも体がひねられるので腸を刺激してくれます。

また、睡眠をしっかりとることで消化機能が正常に働きます。腸のゴールデンタイムと呼ばれるのは、副交感神経が優位になるときで睡眠中です。夜に寝る前は、穏やかに過ごすことで副交感神経が優位になります。そして、腸内環境が良くなれば睡眠の質も上がる、という良い循環になります。
Q.腸活をしているのに、おなかの調子が悪くなることがあるのはなぜですか?
A.おなかの調子が悪いときは、腸活をしすぎの可能性も
免疫が低いときは風邪などを引きやすく、免疫が高すぎる場合は疲れやすい・だるい状態に。また、腸内細菌が過剰な場合はおなかが張ったり、下し気味にもなります。おなかの調子が悪いときは「ばっかり食べ」の傾向にある可能性も。食生活を見直してみましょう。
まとめ
腸活のポイントは「ばっかり食べをしない」「無理せず継続する」ことです。腸活がつらくなるのは一番良くないので、ご自身の体調を見ながら、いろんな食べ物を楽しむ感覚で試してみてください。そうすることで、腸内の菌の多様性も保たれ、良い腸内環境になるはずです。
公開日:2024年12月4日
 國澤 純(くにさわ じゅん)
國澤 純(くにさわ じゅん)
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 医薬基盤研究所 副所長、ヘルス・メディカル微生物研究センター センター長を併任。薬学博士。大阪大学薬学部卒業後、米国カリフォルニア大学バークレー校へ留学。東京大学医科学研究所准教授などを経て2019年から現職。東京大学医科学研究所客員教授なども兼任。著書に『善玉酵素で腸内革命』(主婦と生活者)や『9000人を調べて分かった腸のすごい世界』(日経BP)がある。