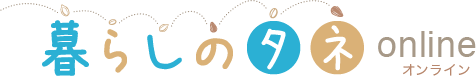不安と戸惑いの介護…
全体像を知っておこう

介護経験のない方はもちろん、すでに介護をされている方も是非ご覧いただきたいシリーズ「教えて介護」。この連載は「介護者手帳」の著者で、介護家族の支援を行っている阿久津美栄子氏に、介護について知っておくべき考え方やポイントを、全6回にわたってご紹介します。第1回目は、介護の全体像を時系列で把握する「介護のロードマップ」に沿って、お話を伺いました。
大変な時期は
永遠には続かない
——介護は、いざ当事者になったら不安という方は多いです。実際はかなり大変なものでしょうか。
阿久津氏(以下、敬称略)
大変か、そうでないかでいうとやはり大変なものです。介護をしている方はどなたも、とても頑張っていらっしゃいます。
そんな印象もあって、今まさに介護が始まろうとしている方は、戸惑いと不安の真っただ中にいることでしょう。介護は突然始まって、大変な状況が果てしなく続くイメージがあると思いますが、実はそうではなく、時系列でみると、①混乱期、➁負担期、③安定期、④看取り期と、大きく4つのステップに分かれています。
こうした全体像を知って、いつどのような状況になるのかが把握できれば、介護者の心理的負担は軽減されるのではないでしょうか。
——介護の始まりは「混乱期」なんですね。
阿久津
混乱期は2つのケースがあります。
1つは認知症の場合。家族など身近な人が気づいて始まることが多いです。もう1つは癌などの病気の場合。こちらは病院での診断を経て始まります。ここから、入院や介護保険制度の申請までを「混乱期」と呼んでいます。
しかし、認知症のケースでは、変化に気がつかないふりをして深刻化させてしまうことがあります。普通に過ごしていたご家族の日常が突然変わってしまったことを受け入れるのは、なかなか難しく時間が必要です。
混乱期は、こうした気持ちの整理ができない状態です。ただ疲労感が出てくるのは、この後に来る「負担期」です。
——負担期とはどういう時期ですか。
阿久津
できないことが増えた不安から、要介護者が介護する方に助けを求めてくる時期です。さまざまな問題に翻弄され、絶望し、お互い疲労困憊という時期です。
——いわゆる「介護離職」もこの時期に多いのでしょうか?
阿久津
混乱期と負担期に多いですね。しかし、介護離職は基本的にお勧めしません。介護する方にも人生があり、その後も続いていきます。例えば50代で離職した場合、再就職はかなり難しいでしょう。そのため、使える制度やサービスは大いに活用して、できるだけ仕事を継続すべきだと思います。
離職される方は、先の見えない不安から、助けてくれる人がいないと思い込みがちです。こういう思考に陥らないためには、介護保険制度や公的な支援などを知ること。
そして、兄弟姉妹、地元の友人など助けてくれそうな人を相談相手に持つなど、ひとりで抱え込まない環境を作ることが大切です。
可能であれば介護が始まる前から情報を集めたり話し合う機会を作るなどして、準備を整えておけるといいですね。
ひと息付ける安定期
——そんな大変な負担期の後に「安定期」があるのは意外です。
阿久津
そうですね、皆さん驚かれます。こうしてロードマップとして全体を可視化すると、それだけで先が見えて安心できますよね。
この時期は、要介護3以上。つまり介護老人福祉施設にも入れる段階です。要介護者と介護する方、双方の物理的な距離ができ、ひと息ついた状態になります。客観的に物事が見られる瞬間でもありますね。
——この時期にすべきことは何でしょうか。
阿久津
安定期では、要介護者が意思疎通できなくなっている場合もあります。そのため、最期をどう過ごすか、延命治療はどうするかなどを、ご本人のお話しを聞けるうちに確認しておくことが理想です。
ただ、そこまでできなかった場合でも、この時期は家族との話し合いを持つのにとても良いタイミングだと思います。遠くにいる親せきほど、延命を求める傾向にあります。家族間でも異なった意見、考えがある場合もありますので、ここで意思をあわせておく方が、後々良いでしょう。
避けられない死別と向き合い
後悔のない看取りを
——ロードマップの最後は「看取り」になっています。当たり前ですが、死を意識するのはやはりショックですね。
阿久津
そうですよね。しかし、ここが重要なポイントです。最期の「死別」に目をつぶって介護を行っている人が非常に多いです。しかし、死を意識しない介護は、必ず大きな後悔が残ります。
要介護者本人が人生の最期をどう過ごしたいのか、その意思疎通が取れないまま看取り期を迎えたとして、果たして本当に望み通りの最期が過ごせるものでしょうか。
もちろん、後悔のない介護というのは、ありません。しかし、早い段階で「死別」を意識することによって、ステップ4の看取り期は、豊かな時間になり得ますので、とても大切だと言えます。
——人生の最期を意識しておくことが重要なんですね。
阿久津
看取り期は、余命宣告を受け、残りの時間をどう過ごすかという時期です。介護をするご家族も、例えば介護休暇を取って、出来る限り一緒に過ごすなど、介護に全力投球できる時期でもあります。この時期を豊かにする鍵は、事前の話し合いと、死をタブー視しないことです。
余談ですが、私は娘が成人する前から、自身の「死」についてよく話しています。最初は嫌がられましたが、家族はいずれ必ず「死別」を経験します。話し合う機会を作ることは、とても大切なのです。
——介護の始まりから終わりまでのイメージを知ることで、ある程度の心構えを持つことも重要ですね。
阿久津
介護は誰しもが初心者で、またある日突然始まります。戸惑いや不安で頭がいっぱいになるのは当たり前のことです。
介護保険制度や公的支援など活用できるものは大いに活用し、困ったら誰かに相談して一人で抱え込まないこと。そして、要介護者ご本人と、どう過ごしたいのか、どのような最期を迎えたいのかについて、話し合う機会を持っていただければと思います。
今回の記事に触れたことをきっかけに、介護する方と介護される方、両方の人生を大切にしてほしいですね。
——ありがとうございました。
次回は、具体的な相談先や注意点についてお伺いします。
※この記事内容は、執筆時点2021年4月1日のものです。
 阿久津 美栄子(あくつ みえこ)
阿久津 美栄子(あくつ みえこ)
1967年長野県生まれ。自身の介護経験からNPO法人UPTREEを立ち上げる。介護者のための「介護者手帳」を製作し、介護家族の支援モデルの確立に注力している。2019年4月「介護あっぷあっぷくん」(介護未経験者・初心者向に向けて介護の基本的な情報、介護保険の仕組み、介護に利用できる公共サービスなどを教えてくれるLINE公式アカウント)をリリース。著書に「ある日、突然始まる 後悔しないための介護ハンドブック」(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、「家族の介護で今できること」(同文書院)。