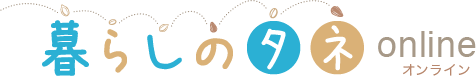季節の不調を解消!
<5月 五月病>

春から新しい環境での生活が始まり、少しずつ慣れてくる5月。「なんとなく気分が沈む」「やる気が出ない」「会社や学校に行きたくない」そんな心や体の変化を感じていませんか?それは、もしかすると「五月病」のサインかもしれません。季節性の病気や症状の原因、予防・対処法を専門の先生に教えてもらうこのシリーズ。今回は「五月病」についてご紹介します。

「五月病」の症状と原因は?
「五月病」は、一般的に4月から5月にかけて現れる心身の不調のことをいいます。医学的な病名ではなく、あくまで通称として広く知られています。特に新社会人や新入生、転勤や転職など新しい環境になった人に多く見られる症状で、環境の変化やストレスに適応しきれず、心や体に反応が出ている状態です。
具体的な症状としては、気分の落ち込みや意欲の低下、集中力の欠如が挙げられます。また、身体的な症状として、頭痛や肩こり、胃の不調、食欲の低下または過多、睡眠障害などが現れることもあります。個人の性格やストレス耐性、さらには新しい環境に対する期待や不安の度合いによっても異なります。
五月病は、日本の文化や社会構造とも関係しています。日本の学校や企業では4月に新年度が始まり、多くの人々が新しい生活環境や職場、人間関係に適応しなければなりません。こうした急激な環境の変化は、大きなストレス源となり、心身に負担をかけることになります。さらに、ゴールデンウィークという長めの休暇があるため、休み明けに現実とのギャップを感じやすいという側面もあります。

~先生からのアドバイス~
「五月病」の予防と対処法

■生活リズムを整える
生活リズムが乱れると自律神経のバランスが崩れやすくなり、心身に疲れが出やすくなります。起きる時間と寝る時間、食事の時間を一定にするだけでも心と体に安定をもたらします。

■休養・睡眠をきちんと取る
心が疲れているときには、頑張り続けることよりも「いったん止まる」ことが効果的です。仕事や学業のペースを少し緩め、静かな時間を意識的に確保したりして、休養を取りましょう。また、人は眠っている間に心と体のダメージを回復しますので、質の良い睡眠を取り、心身をしっかりとリセットしましょう。寝る前は「入浴で体を温める」「テレビやスマホを控える」「音楽を聴く」など、心地良い眠りに導く工夫も大切です。

■食事をしっかり取る
栄養豊富な食事は、体調を維持するだけでなく、心の安定をもたらします。食欲がないからと食べない、逆にストレスで食べ過ぎる、といった偏った食生活は逆効果。適切な量を意識しながら、タンパク質・ビタミン・ミネラルなどバランスの良い食事を1日3食、なるべく規則正しく取ることが大切です。

■軽い運動を習慣づける
1日10分でも体を動かすことで、脳内に「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンが分泌され、気分が前向きになります。ストレッチや散歩、軽いジョギングなど、自分が心地良く続けられる運動でOK。体を動かすことで新陳代謝が活発になり、疲労回復を早める、免疫力を高めるなどの効果もあります。

■頑張りすぎない、無理をしない
新生活や新しい仕事に対して「すぐに慣れなければ」「完璧にこなさなければ」と、無理をしてしまうと疲弊してしまい、結果的にパフォーマンスを低下させてしまう可能性も。まずは今の自分の状態を受け入れることが心の負担を軽減する第一歩。「うまくいかないことがあって当然」くらいに捉えて、自分のペースで物事を進めるといいでしょう。

■人と話す、小さなことでも相談する
ストレスや不安を自分一人で抱え込むと、心の負担は次第に大きくなり、知らぬ間に心身のバランスを崩してしまうことがあります。家族、友人、同僚など、信頼できる人に「なんとなく疲れているかも」と、ただ聞いてもらうだけでも、気持ちが軽くなることがあります。

■小さな「楽しみ」や「ご褒美」をつくる
「仕事や勉強の合間に好きな音楽を聴く」「好きな映画を観る」「推し活をする」…など、自分の機嫌を取る方法を見つけておくと、日々の疲れを癒すことができ、新しい環境を乗り越えるモチベーションも高まるでしょう。

状況が長引くようなら、医療機関への相談も
新しい環境にうまく適応できないことは、決して特別なことではなく、誰にでも起こり得るごく自然な反応です。気分の落ち込みや無気力な状態が数週間以上続く、日常生活に支障が出るほど辛いという場合は、早めに心療内科、メンタルクリニックなどへ相談しましょう。
「病院に行くほどではないかも」と迷う段階でも、「なんとなくいつもと違う」「ちょっとしんどいな」という違和感がある時点で受診することが、結果的に早期回復につながります。早めの対処が、症状の慢性化や悪化を防ぐカギになります。
「五月病」まとめ
五月病は新しい環境に適応しようとする中で、知らず知らずのうちに心や体に負担をかけている状態です。疲労感や無気力感、集中力の低下といった症状があり、頭痛や肩こりなど、体への影響が出ることもあります。肩の力を抜いて、無理をせず、自分のペースで物事を進めるように意識しましょう。また、リラックスできる時間や趣味などの楽しみの時間を持つことで、心に余裕が生まれます。気分の落ち込みや無気力な状態が長引くようなら、心療内科・メンタルクリニックなどへ相談しましょう。
※この記事内容は、執筆時点2025年5月14日のものです。
 森 勇磨(もり ゆうま)
森 勇磨(もり ゆうま)
ウチカラクリニック代表・Preventive Room株式会社代表・産業医・内科医・労働衛生コンサルタント
東海高校・神戸大学医学部医学科卒業。研修後、藤田医科大学病院の救急総合内科にて救命救急・病棟で勤務。救急現場での経験から、「病院の外」での正しい医療情報発信に対する社会課題を痛感し、YouTubeでの情報発信を決意。2020 年2月より「予防医学 ch/ 医師監修」をスタートし、現在チャンネル登録者は42万人を突破し、総再生回数は4000万回を超える。株式会社リコーの専属産業医として、予防医学の実践を経験後、独立。産業医としての「企業と人を健康にする予防医学」、さらには「従来の枠組みにとらわれず、病院の外でできるあらゆる予防医学」のアプローチに挑戦して、1人でも後悔する人を減らしたいという思いから、Preventive Room 株式会社を立ち上げる。現在はオンライン診療に完全対応したクリニック「ウチカラクリニック」を通じて、オンライン診療の適切な形での社会実装、セルフケアの推進に取り組んでいる。
https://uchikara-clinic.com/