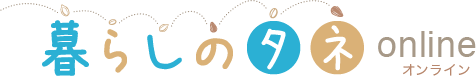季節の不調を解消!
<10月 インフルエンザの予防>

毎年冬に流行する「インフルエンザ」。高熱や全身のだるさなど、突然の症状で体調を大きく崩してしまうため注意が必要です。このような季節性の不調の症状や原因、予防・対処法を専門の先生に教えてもらうこのシリーズ。今回は、インフルエンザの原因や予防法、万が一かかってしまったときの対処法について、専門家のアドバイスを交えてご紹介します。
まずはセルフチェック!
以下の症状に多く当てはまる場合、「インフルエンザ」の可能性があります。

「インフルエンザ」の原因と症状は?
インフルエンザの原因や、症状がどのように出るのかを知っておくことが、早期対応と重症化予防の第一歩です。
■飛沫・接触感染に要注意
インフルエンザは、A型・B型・C型のインフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症です。主な感染経路は飛沫感染や接触感染で、くしゃみや咳、ウイルスが付着した物に触れることで広がります。特に冬は空気が乾燥しやすく、ウイルスが活発になり感染しやすい環境となるため、注意が必要です。
■突然の高熱や全身のだるさが主な症状
インフルエンザにかかると、突然の高熱が出ることが特徴です。同時に、全身のだるさや筋肉痛、関節の痛み、喉の痛みや頭痛を伴う場合もあります。風邪と比べて症状が急激で強いのが特徴です。子どもでは、嘔吐や下痢を伴うこともあります。さらに高齢者や免疫力が低下している人は、肺炎などの合併症を起こしやすく、重症化のリスクが高いため、早めの対応を行いましょう。

風邪や他の感染症との違い
インフルエンザは風邪や他の感染症と似た症状が出ることもありますが、発症の早さや症状の重さ、原因には違いがあります。それぞれの特徴を知っておくことで、早期に見分けて適切に対処する手掛かりになります。
| インフルエンザ | 一般的な風邪 | 新型コロナ | 胃腸炎 | アレルギー症状 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発症時期 | 11月〜3月 | 一年中 | 一年 | 主に冬 | 春・秋に多い |
| 主な原因 | ■インフルエンザウイルス(A型・B型・C型) ■飛沫・接触感染 |
■かぜウイルス(ライノウイルスなど) | ■新型コロナウイルス(SARS -CoV-2) ■飛沫・接触・空気感染 |
■消化器系ウイルス(ノロウイルスなど) ■接触感染 |
■花粉やハウスダストなどのアレルゲン |
| 主な症状 | ■38℃以上の高熱 ■全身のだるさ ■筋肉痛 ■頭痛など |
■微熱〜37℃台の発熱 ■のどの痛み ■鼻水 ■咳など |
■37.5℃〜38.5℃程度の発熱 ■咳 ■咽頭痛 ■全身のだるさ ■味覚・臭覚異常 ■頭痛 |
■嘔吐 ■下痢 ■腹痛 ■軽度の発熱など |
■鼻水 ■くしゃみ ■目のかゆみ ■咳など |
| 特徴 | 突然の発症で、症状が急激に悪化することが多い | 全身症状は比較的軽く、だるさも軽度 | 無症状や軽傷者も多い。高齢者および基礎疾患のある人は重症化リスクが高い | 主に消化器症状が中心。嘔吐や下痢で水分が失われるため水分補給が重要 | 発熱はほとんどなく、症状は季節やアレルゲンに左右される |
~先生からのアドバイス~
「インフルエンザ」の
予防と対処法

インフルエンザは、症状が急に悪化することがあるため、日頃からの予防と発症した場合の早期の対処が重要です。
【予防】ワクチン接種
毎年、流行前にワクチンを接種することで重症化を防ぐことができます。
【予防】手洗い・うがい・マスクの着用
ウイルスの侵入を防ぐ基本的な対策です。外出時はマスク着用を、外出から帰ってきたら、手洗い・うがいを欠かさず行いましょう。
【予防】乾燥対策
加湿器などで室内の湿度を保つと、ウイルスが空気中に漂いにくくなり、感染リスクを下げられます。定期的に窓を開けて換気も行いましょう。
【予防】栄養・睡眠などの健康管理
健康的な生活を送り、免疫力を高めることは、あらゆる病気の予防の基本です。日々の生活習慣を整え、感染しにくい体づくりを意識しましょう。
【対処】医療機関の受診
症状が出たら、早めに受診しましょう。発症48時間以内であれば抗インフルエンザ薬が処方される場合があります。
【対処】水分補給
高熱や嘔吐・下痢の症状では体内の水分が失われやすく、脱水になりやすいため、こまめな水分補給が大切です。
【対処】解熱薬や症状緩和薬の使用
医師や薬剤師に相談し、適切な薬を服用しましょう。自己判断での市販薬の使用は避けましょう。

「インフルエンザ」まとめ
インフルエンザは、急な高熱や全身のだるさ、筋肉痛などの症状が特徴で、主に冬に流行する感染症です。予防の基本は、ワクチン接種や日常生活での健康管理にあります。もし感染した場合は、早めに医療機関で対処することが、重症化を防ぐために非常に重要です。
感染した場合や流行時には、周囲への感染を防ぐため、無理な外出を控えることが大切です。学校や職場に行かず、体をしっかり休め、回復を早めることを優先しましょう。
※学校保健安全法では、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」を出席停止期間として定めています。この期間は周囲への感染リスクを減らすため、外出を控えることが推奨されます。
※この記事内容は、執筆時点2025年10月8日のものです。
 森 勇磨(もり ゆうま)
森 勇磨(もり ゆうま)
ウチカラクリニック代表・Preventive Room株式会社代表・産業医・内科医・労働衛生コンサルタント
東海高校・神戸大学医学部医学科卒業。研修後、藤田医科大学病院の救急総合内科にて救命救急・病棟で勤務。救急現場での経験から、「病院の外」での正しい医療情報発信に対する社会課題を痛感し、YouTubeでの情報発信を決意。2020 年2月より「予防医学 ch/ 医師監修」をスタートし、現在チャンネル登録者は42万人を突破し、総再生回数は4000万回を超える。株式会社リコーの専属産業医として、予防医学の実践を経験後、独立。産業医としての「企業と人を健康にする予防医学」、さらには「従来の枠組みにとらわれず、病院の外でできるあらゆる予防医学」のアプローチに挑戦して、1人でも後悔する人を減らしたいという思いから、Preventive Room 株式会社を立ち上げる。現在はオンライン診療に完全対応したクリニック「ウチカラクリニック」を通じて、オンライン診療の適切な形での社会実装、セルフケアの推進に取り組んでいる。
https://uchikara-clinic.com/