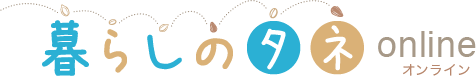〜認知症を考える〜最期まで家族は家族のままでいい

患者と家族はどのように認知症と向き合えばいいのか。認知症専門病院で多くの患者とその家族に接してきた今井氏に話を伺いました。 ◇インタビュー◇ 医療法人 社団翠会 和光病院 院長 今井 幸充 氏
認知機能が低下して生活に支障が出る状態が認知症
脳の何らかの障害により認知機能が低下し、日常生活に混乱が見られ、介護が必要になると、認知症を疑います。一方で「もの忘れ」は記憶の障害であり、それが日常生活上問題なければ認知症ではありません。生活が正常に営まれているかどうかが認知症ともの忘れの大きな違いです。例えば、同じ品物を何度も買ってくる、料理の味付けが分からなくなる、お金の管理がルーズになって銀行から不必要に大金を引き出す、など生活上の混乱や困った行為が見られたら認知症を考えなければいけません。
生活に支障はないけれど、もの忘れが目立つので記憶検査を実施してみると、平均点よりやや低い人がいます。この状態を「軽度認知障害(MCI)」といい、認知症ではありません。しかし軽度認知障害の人の約半数が4年以内にアルツハイマー型認知症になるというデータもあり、認知症のハイ・リスカーとして注意が必要です。
いずれにしても、早期発見・早期診断が重要でアルツハイマー型認知症と診断された場合は、抗認知症薬の投薬により認知症の進行をある程度抑えることができます。軽度認知障害の場合でも、認知症予防に効果的な生活を営むことで、認知機能が維持される可能性があります。例えば、できるだけ外部の人と接する機会を設け会話を楽しむ、散歩などの運動する時間を持つ、塩分や糖分を控え健康的な食事に心がける、等が認知症予防に大切です。
家族あるいは本人自身が、生活上困るもの忘れに気付いたら、できるだけ早い時期に受診することを勧めます。それにより、認知症と診断されたとしても、これからの生活の在り方や地域の介護福祉サービスの利用について、家族と予め話し合うことができ、家族は、本人の今後の生活の在り方を考えることができます。
ケアも治療の一環。家族を含めたケアが重要
認知症は治る病気ではありませんので医療が何をなすべきか、大変難しい課題です。認知症の診断はもとより、その後の治療について抗認知症薬の使用を考慮しますが、これらの薬で認知症を治すことはできません。「ケアも治療の一環」と考え、良いケア環境を提供することも本人とその家族にとって必要な医療サービスの一環だと思います。
患者とその家族に対する医療ケアは、たとえ認知症の専門医であっても、ひとりでできるものではありません。医療・看護の専門家と、介護・社会福祉の専門家が、それぞれの専門性を発揮し、連携していくことが必要です。
例えば、当院では、認知症専門外来に認知症看護外来を併設しています。そこでは、認知症看護認定看護師が、認知症の症状に応じて、日常生活での対処の仕方、日々の食事・排泄・入浴などの介助について、相談支援を行っています。
また、当院を受診した認知症の人には、必ず担当のケースワーカーを置き、電話などによる家族からの相談窓口となっています。相談内容によっては、医師、薬剤師、看護師と連携して対応していきます。
介護保険サービスなど地域の社会福祉サービスを希望する場合は、当院のケースワーカーや担当看護師が、地域の認定介護福祉士との橋渡し役を担います。さらに、自宅介護が困難となり、介護施設への入所を希望する場合や身体合併症のために入院が必要な時は、精神保健福祉士が支援し、それらの施設を紹介しています。
このように、様々な専門職が患者と家族に介護支援を行っていますが、他にも在宅介護をサポートする介護支援専門員(ケアマネジャー)や認知症ケア専門士が院内・院外で活動をしています。同居家族が一人で認知症介護を抱えることは無理ですので、地域のケアマネジャーに相談して居宅介護サービスを大いに利用してください。

一番大切なのは、安心の下で生活すること
認知症の人を世話する家族にとって大切な役割は、認知症の人が、残された時間を安全にそして安心して生活できる環境を確保してあげることです。それには、認知機能が衰える前に、本人が望む終末期の過ごし方を一緒に、時間をかけて話し合ってください。その結果、本人が「認知症になっても安心、元気で暮らしたい」という前向きな気持ちになれば、それは素晴らしいことです。
しかし、一人ひとりに異なる生活スタイルがあるように、家族が考える本人の終末期の在り方と本人の思いが必ずしも一致するわけではありません。これまでの本人と家族の関係性についても両者の捉え方は異なります。家族が認知症の人の支援の在り方を考慮する時には、家族の考えを押しつけるのではなく、本人の思いや希望についても念頭に置いた支援が重要です。
臨床の場面では、よく家族の果たすべき役割について問われますが、それは他者が明確に答えられる問題ではありません。家族と認知症の人が、これまで一緒に過ごしてきた時間の中で築きあげてきた関係性は、双方の思いをお互いに理解し合う重要な要素です。それ故、その人と過ごした歴史の中に、家族の世話の在り方が見えてくるのではないかと考えます。
専門家の支援を受け、家族が介護の負担や苦しみから解放されれば、「本人と介護人」という関係から、「家族の一員」という元の関係に戻れるでしょう。家族は、最後の最後まで家族であってほしいので、介護専門職の人を在宅介護に大いに利用し、介護者としての時間ではなく、その人と、大切な家族としての時間を過ごしてほしいと願います。
認知症への支援で考えると介護保険制度は成功だった
ひと昔前に比べ、認知症を取り巻く介護環境は大きく改善しました。認知症に対する理解が進み、利用できる施設や社会支援の仕組みなど、社会的なインフラも整ってきました。その点では、日本の介護保険制度は成功したと思います。しかし、まだ多くの課題が残されています。居宅サービス給付は、財源の関係でしょうか、抑制される傾向にあるように感じます。例えば、夫婦2人が、それぞれの高齢の両親、合計4人の介護をしなければいけないとしたらどうでしょう。まず自宅での介護は無理で、誰が介護を担うのかという問題の他に、そもそも認知症の人の居場所をどうするのか、という問題も出てきます。人口減少・高齢化社会の日本にあって“介護を社会化する”介護保険制度は必要不可欠な制度ですが、多くの高齢者が「最後は安心して終わりたい」と口にします。認知症の人の“終の棲家”が十分に整備されているとは感じていないようです。現状では、高齢者向け介護施設や養護施設が数多く開設されていますが、それらの施設で認知症の人の住まい方、認知症の人にとっての安全で安心して生活できる“終の棲家”とは何か、十分な議論がされているか疑問です。ご家族も自分の事として認知症の人が住まう場所を検討してみてください。
どんなに必要な制度でも、利用者が納得のいくサービスを受けられなければその制度は継続しません。つまり、今後の超高齢化社会での社会サービスの在り方については、提供する側の考えも必要ですが、利用者の立場に立ったサービスをもっと検討していかないと介護保険制度は続かないと思います。ぜひ、皆さんも自分の事として、今の介護保険サービスは、これで良いのか、そして将来どうあるべきかを考えてみてください。私も読者の皆さんも、将来の高齢者なのです。

1984年、聖マリアンナ医科大学大学院卒業、1989年、聖マリアンナ医科大学神経精神科講師、1994年、米国ワシントン州立大学ワシントン大学客員研究員、1996年、聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室助教授、同大学東横病院精神科部長。2001年、日本社会事業大学大学院教授を経て、2012年から現職。2016年〜2018年、日本認知症ケア学会理事長。
※この記事は、都道府県民共済グループ発行「介護のことがわかる本」の抜粋です。
内容は、執筆時点2024年8月1日のものです。