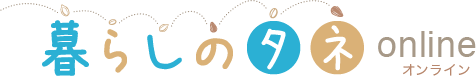どれぐらいもらえる?出産時の一時金と手当金

「子どもを産むにもお金がかかるし…」と不安を感じている方は、出産をサポートする公的制度があるのをご存じでしょうか?ここでは「出産手当金」と「出産育児一時金」をご紹介。受給条件が異なりますので、予めしっかり確認しておきましょう。
健康保険には、出産に伴う出費や産休中の収入をカバーする保障もあります。妊娠85日(4カ月)以後の早産、流産、人工妊娠中絶のケースも対象となります。
50万円の「出産育児一時金」
妊娠中の検診や出産時の入院には、医療措置が必要になるトラブルが生じないかぎり、健康保険が使えません。しかし、健康保険から1児につき50万円(2023年4月〜)の「出産育児一時金」が支給され、妊娠・出産に伴う費用の保障ととらえることができます。本人が被保険者として健康保険に加入していればその制度から、扶養家族となっている場合は夫の加入している制度から受けられます。
■直接支払制度
給付金が入院先の医療機関に直接支払われる「直接支払制度」を利用すれば、事前にまとまった入院費が準備できなくても安心です。差額は後で精算します。
収入をカバーする「出産手当金」
働く女性の場合、勤め先から産休中の給料が支払われないか少なければ、自分が被保険者として加入している健康保険から「出産手当金」が支給されます。給料が全額支払われるようなら出産手当金の支給はありませんが、産休中の給料の額が出産手当金額より少ない場合は、その差額が受け取れます。
支給額の計算方法は少し複雑で、1年以上勤めている人の場合だと、支給開始される前1年間の給与をもとに1日あたりの金額を算出します。おおむね収入の3分の2を目安にすればいいでしょう。
なお、国民健康保険には出産手当金の制度はありません。
※記事内容は、執筆時点2023年8月1日のものです。
 浅田 里花(あさだ りか)
浅田 里花(あさだ りか)
ファイナンシャルプランナー、株式会社生活設計塾クルー取締役。コンサルティングや新聞・雑誌などへの原稿執筆、セミナー講師を行う。東洋大学社会学部の非常勤講師としても活躍。代表的な著書に『Q&Aで学ぶライフプラン別営業術』(近代セールス社)など。